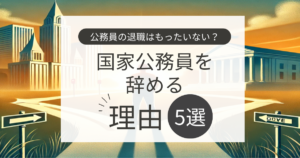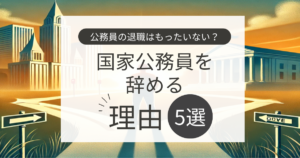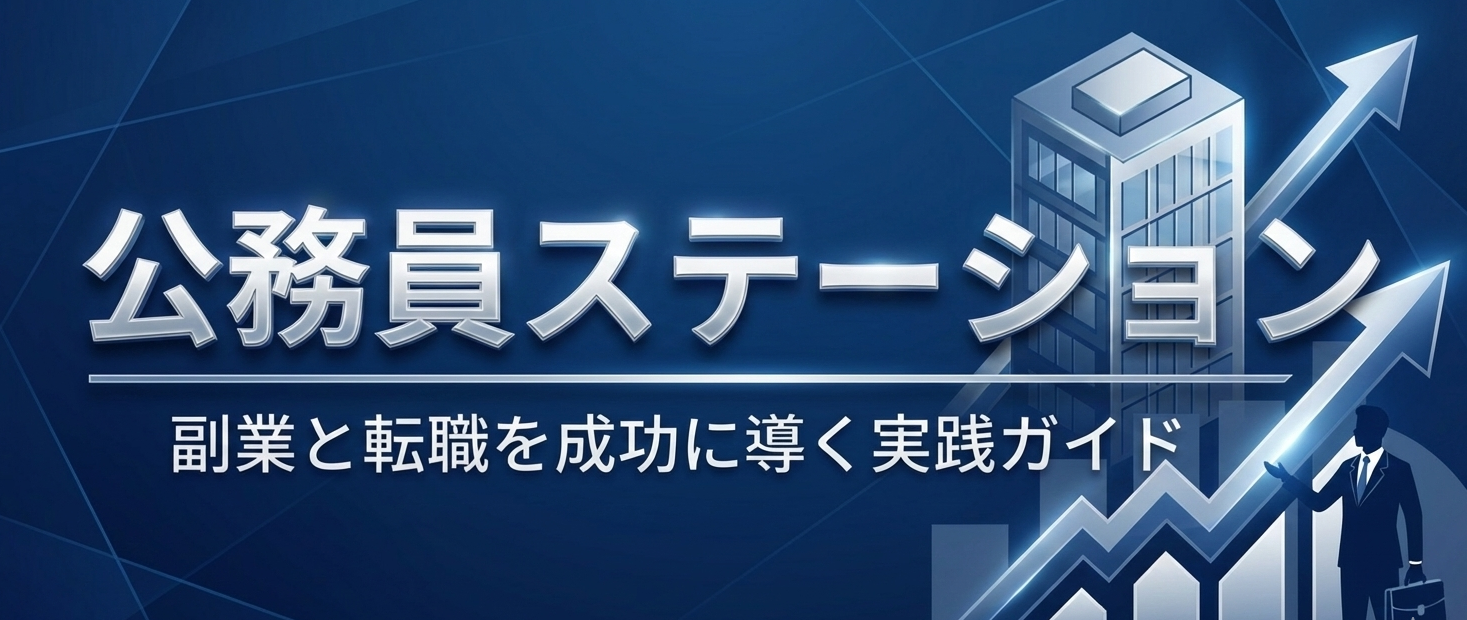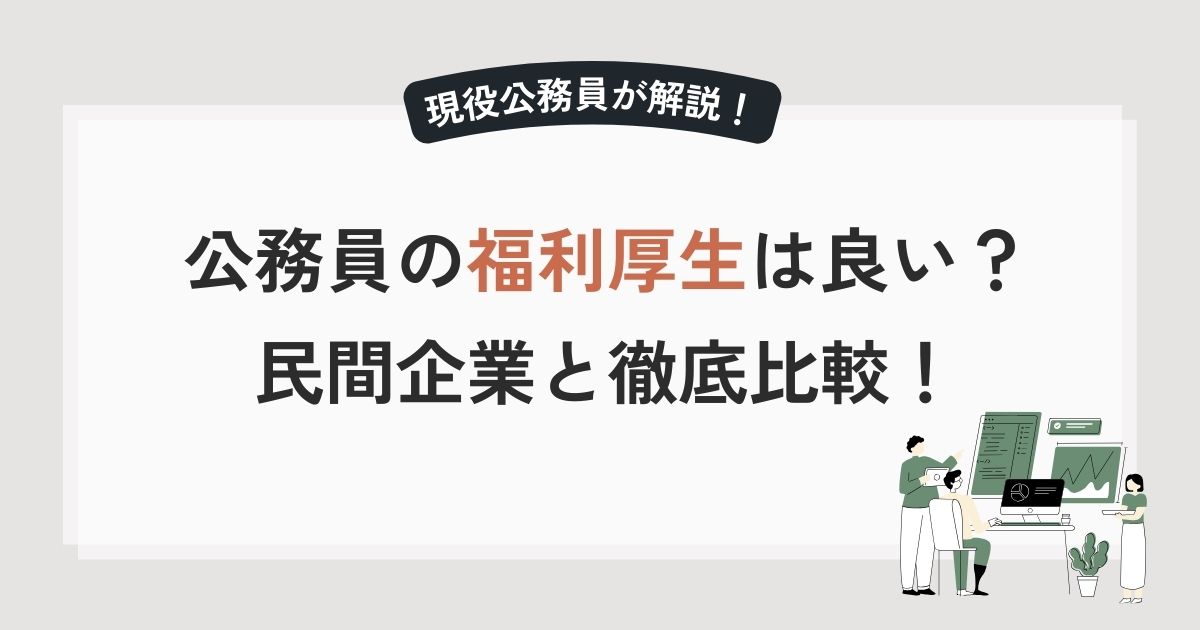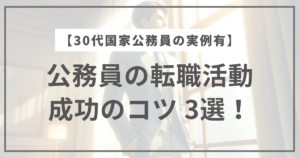よしと
よしとこんな疑問を解決します!
入所してから人事評価で「非常に優秀」を取り続けている技術系国家公務員一般職10年目のよしとが、公務員の副業について解説します!
しかし、公務員を辞めることを真剣に考え、転職活動に挑戦しました。
結果として内定を3社からいただいたものの、家庭の事情で辞退。
現在は、来年度の転職を目指して準備中です。
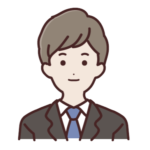
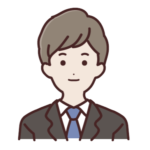
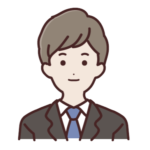
公務員は福利厚生が手厚くて安心だよね
そんなイメージを持っている方は多いのではないでしょうか。
たしかに、家賃の安い官舎や共済組合による医療費の補助など、制度としては一見充実しているように見えます。
しかし、実際に転職サイトなどで大手企業の福利厚生を見ていると、「あれ、公務員よりも福利厚生いいんじゃない?」と感じることがよくあります。
もちろん、隣の芝が青く見えるだけかもしれません。
ですが、制度の柔軟性や選択肢の多さといった点では、民間企業の方が進んでいると感じることもあるのが正直なところです。
本記事では、国家公務員として働いている筆者の実体験をもとに、「公務員の福利厚生は本当に優れているのか?」というテーマで深掘りしていきます。
民間企業との比較表も交えながら、公務員の制度の実態とそのメリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。
長文になっているので、公務員と民間企業の比較表だけみたいという方はここをクリックしてください。
これから転職を考えている方、公務員のキャリアを見直したい方にとって、判断材料となるはずです。
公務員の福利厚生の主な内容


国家公務員の福利厚生は、法令や制度に基づいて全国で共通化されており、一定の安定感と公平性が特徴です。
ここでは、国家公務員が受けられる主な福利厚生を紹介します。
住宅手当・宿舎制度
- 住宅手当
民間賃貸住宅に住んでいる場合、一定の条件を満たせば、月額最大28,000円(令和7年度時点)の住宅手当が支給されます。
家賃によって支給額は異なりますが、月額3万~6万円の賃貸では、家賃の40〜50%程度が補助されることが一般的です。 - 宿舎制度(官舎)
職場近くに国家公務員宿舎が整備されており、家賃は周辺相場より安価です(1〜3万円台が中心)。
築年数は古めな物件が多いですが、家賃の安さには大きな魅力があります。
ただし、当たり外れが激しく築50年程度のボロアパートも平気に残っているのが現状です。
独身者によってはコスト面で魅力がありますが、世帯向けにはおすすめできない場合もあります。
(出典:人事院 令和7年4月 国家公務員の諸手当の概要)
扶養手当・広域異動手当
- 扶養手当
配偶者:月額6,500円(※2025年度から段階的に減額・廃止、2026年度に完全廃止予定)
子ども:2025年度は11,500円、2026年度には13,000円へ増額予定 - 広域異動手当
転勤などで60km以上の広域異動を行った場合、距離に応じて3年間の加算手当が支給されます。
たとえば300km以上の異動では、給与の10%相当が支給されるため、手当としてのインパクトは大きいです。
引越し費用も別途補助制度が整備されています。
(出典:人事院 令和7年4月 国家公務員の諸手当の概要)
共済組合(医療・年金)
国家公務員は「国家公務員共済組合」に加入しています。地方公務員は「地方公務員共済組合」があるかと思います。
- 医療
医療費の自己負担は原則3割ですが、附加給付として、一定額を超えた医療費は後日還付される仕組みがあります。
高額療養費制度と合わせて、急な出費にも対応できる安心感があります。 - 年金
2015年の制度改正により、国家公務員も民間と同様に厚生年金に統一されました。
ただし、国家公務員には独自の「退職等年金給付制度」(いわゆる年金の3階部分)もあり、上乗せの年金がある点が特徴です。
(参考:人事院 退職等年金給付制度)
育児・介護休暇制度
- 育児休業
子どもが3歳になるまで取得可能です(無給期間あり)。
近年は男性職員の取得も増加傾向にあり、職場全体で育児参加が進んでいます。 - 介護休業
家族の介護が必要な場合に利用可能で、長期的な休業にも対応しています。
また、復職後の支援制度も整っており、ライフイベントに配慮した制度設計となっています。
(参考:人事院 妊娠・出産・育児・介護の仕事の両立支援ハンドブック(令和7年4月改訂))
年次休暇・特別休暇
- 年次有給休暇
採用1年目は15日、2年目以降は年20日が付与され、最大40日まで繰り越しが可能です。 - 夏季休暇
お盆時期を中心に、3日間程度の夏季休暇が取得できます。業務状況に応じて、分割取得も可能です。 - その他の特別休暇
看護休暇、結婚、忌引、出産、ボランティアなど、さまざまなライフイベントに対応した休暇制度が整備されています。
(参考:人事院 休暇制度の概要)
退職金制度
退職時には、勤続年数や退職理由に応じた退職手当が支給されます。
勤続20年以上で定年退職した場合、1,000万円以上となることも珍しくありません。
内閣官房内閣人事局が発表した「令和5年度 退職手当の支給状況」によると、国家公務員のうち、常勤職員が定年まで勤めた場合の退職金平均額は、約2,147万円です。
(出典:内閣官房:令和5年度 退職手当の支給状況)
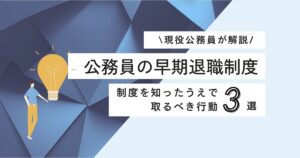
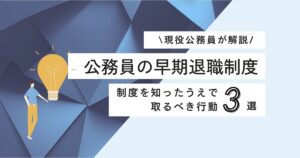
福利厚生サービス(外部連携)
各省庁では、福利厚生の一環として、福利厚生代行サービス(ベネフィット・ワン等)を導入している場合があります。
- 宿泊施設やレジャー施設、映画館、ショッピング、育児・介護サービス、引っ越し、健康診断、eラーニングなど、利用可能なサービスは140万件以上。
- ただし、各省庁によって契約内容や利用範囲が異なるため、対象職員や地域によって使い勝手に差があります。
個人的には、「使える施設が少ない」「割引額が小さい」と感じることも多く、私は映画館の割引ぐらいしか利用していません。
民間企業の福利厚生





公務員の世界で暮らしていると、民間企業の福利厚生がわからないですよね。
特に最近は、給与だけでなくどれだけ生活や働き方をサポートしてくれるかに価値を置く人が増えているため、福利厚生に力を入れている企業も多くあります。
民間企業の福利厚生内容を把握しましょう。福利厚生は大きく分けて次の2種類があります。
法定福利厚生(法律で義務付けられているもの)
すべての企業が必ず導入しなければならない福利厚生です。
- 健康保険:従業員や家族の医療費負担を軽減する保険
- 厚生年金保険:老後や障害時の生活を支える年金制度
- 介護保険:40歳以上の従業員が対象となる介護費用の保険
- 雇用保険:失業時や育児・介護休業時の所得を補償
- 労災保険:業務中や通勤中の事故・病気を補償
- 子ども・子育て拠出金:子育て支援のための拠出金
法定外福利厚生(企業が自主的に導入するもの)
企業ごとに内容や充実度が大きく異なります。従業員の満足度や働きやすさ向上のために導入されることが多いです。
- 住宅手当・家賃補助:住居費の一部を会社が負担
- 通勤手当:通勤にかかる交通費の支給
- 食事補助・社員食堂:昼食代の補助や社内食堂の提供
- 慶弔金(結婚・出産・弔事など):従業員や家族の慶事・弔事に対する金銭的支援
- 特別休暇・病気休暇:有給休暇以外の休暇(リフレッシュ休暇、ボランティア休暇など)
- 育児・介護支援:育児休業、時短勤務、託児所の設置など
- 財形貯蓄制度・持株会:従業員の資産形成を支援
- 健康診断・人間ドック補助:定期健康診断や人間ドック費用の補助
- レジャー・宿泊施設の割引:提携施設の利用割引や旅行補助
- ユニークな制度:カフェテリアプラン、失恋休暇、ペット同伴出勤など、企業独自の福利厚生も増えています
法定福利厚生はすべての企業で共通ですが、法定外福利厚生は企業ごとに内容・充実度が大きく異なります。
これらの制度は企業ごとに差があり、特に大企業では手厚い傾向があります。
令和3年就労条件総合調査によると、常用労働者1人あたりの法定外福利費用(月平均)は、
- 従業員30~99人の企業:4,414円
- 従業員1,000人以上の企業:5,639円
(出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」)
中小企業でも独自の制度導入が進んでおり、福利厚生の充実度が企業の魅力を左右する重要な要素となっています。
福利厚生の充実は、従業員の働きやすさや会社への満足度、採用力の向上にもつながります。
企業の代表的な福利厚生制度:公務員との比較


民間企業の中には、独自に充実した「法定外福利厚生」を整備している企業が数多く存在します。
以下、カテゴリごとに代表的な制度と企業事例を紹介します。
① 住宅支援
住宅手当・家賃補助
都市部での生活コストが高い中、住宅手当は最も恩恵を感じやすい福利厚生の一つです。
多くの企業では月額3~7万円程度を支給しており、条件を満たせば長期的な経済的支援となります。
- 住友重機械工業:家賃の65%を補助(単身者:上限45,500円、複身者:上限65,000円)
- 大林組:借家・持家いずれでも住宅手当を支給(持家でも月額2万円)
- INPEX:35歳未満で1都3県居住者に月5万円を支給
(出典:住友重機械工業採用サイト、大林組の福利厚生|OpenMoney、INPEX採用情報)
社宅・借上げ社宅制度
企業が所有する独身寮や家族社宅、もしくは民間物件を借り上げた社宅を月額1~3万円で利用できる制度です。
特に転勤が多い企業では、転居・引越し費用も会社負担となるケースが一般的です。
- 旭化成:独身寮・社宅制度あり。東京23区内でも2万円以下で居住可能。
- サントリーロジスティクス:借り上げ社宅制度あり(最大75%補助)。
- 日本製鉄:世帯向け社宅は約2.5万円/月。独身者向けの独身寮が約1.5万円/月
(出典:旭化成の福利厚生OpenMoney、サントリーロジスティクス採用情報、日本製鉄採用情報)
(出典:旭化成の福利厚生 OpenMoney、サントリーロジスティクス株式会社 採用情報、日本製鉄 採用情報)
② ライフイベント支援
結婚・出産祝い金
結婚や出産の節目に、祝い金を支給する制度を導入している企業が増えています。
- アキュラホーム:「しあわせ一時金制度」により、第1子30万円、第2子50万円、第3子以降は100万円を支給
- 日鉄物流:結婚祝金3万円
- 明治安田生命:出産育児一時金として1人50万円を支給
(出典:株式会社AQ Group 採用サイト、日鉄物流株式会社 採用情報、明治安田生命 福利厚生)
扶養手当・子育て支援手当
企業によっては、子ども1人あたり月1〜3万円の手当を支給しています。
- JR東日本:1人目1万円、2人目1.5万円、3人目2万円
- ラクス:子1人3万円/月、2人 5万円/月、3人以上 6万円/月を18歳まで支給
(出典:JR東日本 子育て等に関する支援の拡充、株式会社ラクス キャリア採用)
③ 健康・医療支援
健康診断・人間ドック補助
法定健診に加え、人間ドックなども補助対象とし、自己負担が軽減している企業もあります。
・日本郵政:人間ドック、がん検診、脳ドックを補助対象
(出典:日本郵政共済組合)
メンタルヘルスケア
産業医やカウンセラーによる定期面談、ストレスチェック制度などを導入している企業も増加しています。
フィットネス・健康支援制度
職員やその家族の健康増進、疾病予防、生活習慣病対策などを目的として、企業がサービスを提供していることもあります。
・楽天:託児所やカフェテリア、ジムや鍼灸・マッサージなど、健康維持に役立つサービスを優待価格で利用可能です。
(出典:楽天公式キャリアサイト)
④ 働き方と休暇支援
有給休暇取得推進・リフレッシュ休暇
勤続年数に応じて、特別休暇や旅行補助金を支給する企業もあります。
・ドトールコーヒー:年に一度最大連続9日間のリフレッシュ休暇を取得
(出典:ドトールコーヒー 採用サイト)
男性育休の取得支援
近年は男性の育休取得を積極的に支援し、取得率100%を目指す企業も多くなってきています。
転勤手当の充実
転勤を理由に退職者が増えているため、金銭的なフォローをする企業もあります。
・大成建設:2025年度から転勤に伴う一時金を最大100万円
・東京海上日動火災保険:転勤サポート手当があり、新卒社員に対して、転居を伴う転勤に同意した場合は月額最大約41万円の給与が支給されます。
(出典:日本経済新聞、大成建設最大100万一時金、東京海上日動 採用情報)
⑤ 自己啓発・教育支援
資格手当
会社が業務に関連する資格取得者に対して毎月の給与や一時金として支給する手当です。
・JR東海コンサルタンツ:資格手当が充実している(例:技術士2万/月(報奨20万)、一級建築士1万/月(報奨8万))
(出典:JR東海コンサルタンツ 福利厚生)
社内研修制度・社内大学
企業が社内に設置する研修制度の一種で、社員が自主的に学ぶ場を与える企業もあります。
・KDDI:社員のキャリア形成を支援する「社内大学」制度あり。スキルやキャリアプランに応じた専門講座が用意されています。
(出典:KDDI 採用情報)
副業制度
厚生労働省は2018年に副業・兼業に関するガイドラインが新設され、副業を解禁する企業が増えています。
- 三菱地所:社員のモチベーション向上とビジネスモデル革新を目的に、副業を条件付きで解禁
(出典:三菱地所 各種制度)
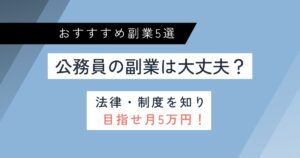
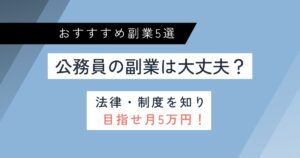
⑥ 退職金
中央労働委員会「令和5年 退職金・年金調査」によれば、資本金5億円以上かつ従業員1,000人以上の企業における退職金は以下のとおりです。
- 大卒:2,140万円
- 高卒:2,020万円
一方、公務員の定年退職金は平均2,147万円とされ、大企業と同水準であることがわかります。
(出典:厚生労働省 中央労働委員会 令和5年調査)
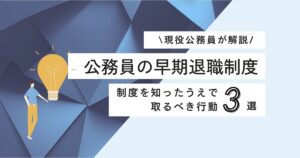
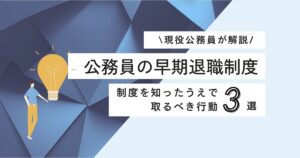
⑦ 福利厚生サービス代行・選択制制度
外部福利厚生サービスの利用
- 福利厚生倶楽部(リロクラブ)
約12万のコンテンツ、350万種以上のサービス(2024年時点)を用意。旅行、レジャー、フィットネス、グルメ、ショッピング、育児・介護、自己啓発、健康支援など多岐にわたるメニューが揃っています。 - ベネフィット・ステーション(ベネフィット・ワン)
グルメ、レジャー、ショッピング、eラーニング、育児・介護、引っ越しなど、140万件以上のサービスを優待価格で利用可能です。
カフェテリアプラン制度
従業員がポイントを使って、住宅補助・旅行・育児・自己啓発など自分に合ったメニューを自由に選択できる制度です。
個人ニーズへの対応力が高く、公務員制度に比べて柔軟性に富んでいます。
こうした制度は、企業独自に設計されるため柔軟性があり、職場文化や従業員層に応じて進化し続けています。
民間企業のなかには、働きやすさを訴求する“福利厚生ブランディング”を積極的に展開する企業もあり、公務員制度と比べて自由度の高さが際立ちます。
公務員vs民間企業 福利厚生の比較
公務員と民間企業(大手の事例)における福利厚生の違いを簡単にまとめた比較表です。
福利厚生は、企業にもよるものなので詳細は興味のある企業HP等で調べてみてください。
| 福利厚生項目 | 公務員 | 民間企業(大手の事例) |
|---|---|---|
| 住宅手当・社宅 | 上限ありの住宅手当、官舎あり | 家賃65%補助、社宅あり |
| 結婚・出産祝い金 | 法定範囲内の手当(例:出産手当金) | 第1子30万円、第3子以降100万円など |
| 扶養・子育て手当 | 子1人 約1.2万円 | 子1人あたり月1~5万円支給など |
| 健康診断・人間ドック | 人間ドックの補助もあり | 脳ドック・がん検診補助などもあり |
| 年金制度 | 国民年金+厚生年金+退職等年金給付 | 国民年金+厚生年金+企業年金 |
| メンタルケア制度 | カウンセリングなどあり | ストレスチェック・産業医面談等あり |
| 有給休暇制度 | 年20日付与(繰越あり) | 年20日+リフレッシュ休暇など |
| 育児休業(男性含む) | 子が3歳になるまで取得可能 | 最長子が2歳になるまで |
| 資格手当 | なし | 月1〜3万の手当や報奨金有 |
| 副業制度 | 原則禁止 | 副業可能の企業も有り |
| 退職金 | 平均約2,147万円 | 大卒で約2,140万円 |
| 福利厚生サービス | 各所属による代行サービス等 | リロクラブ等、カフェテリアプランなど多様な外部サービス利用 |



単純な比較は難しいですが、「公務員より福利厚生が充実している企業もある」というのは間違いありません。
公務員の福利厚生は悪い?メリット・デメリット
- 制度の安定性
- 手厚い生活支援
- 休暇制度が取りやすい
公務員の福利厚生は、法律に基づいて全国的に共通の基準で整備されており、自治体や職場による格差が小さいのが特徴です。
また、景気変動の影響を受けにくく、制度が長期的に安定して運用される安心感があります。
内容面では、通勤手当・住宅手当・扶養手当・人間ドック補助・医療保険・年金・慶弔給付金など、生活全般を広くカバーする手当が揃っており、一定水準の生活サポートが受けられる点は魅力です。
転職活動をした際、扶養手当や住宅手当もない企業があって驚きました。
会社によっては手当がない分、基本給が高くなっている企業もあるようです。
さらに、年間休日が一部の民間企業より多いこともあり、年次有給休暇も採用と同時に付与されるため、比較的休みが取りやすい職場環境です。
病気休暇や特別休暇も整備されており、私生活や療養の両立がしやすい職場環境が期待できます。
- 大手企業よりも劣ることがある。
- 制度自体は充実しているが、利用率が低いものがある。
- 働き方の柔軟性が限定的
民間企業、特に大手では独自のカフェテリアプランやリフレッシュ休暇、旅行補助、転勤手当などのユニークな福利厚生を導入しており、“魅せる福利厚生”として企業ブランディングにも活用されています。
一方、公務員制度は税金を財源とするため、自由度が低く、世論の監視や制度見直しの圧力が強いのが実情です。
また、制度はあっても実際には「忙しくて休暇を使えない」「制度を知らない」「上司の目が気になって休めない」など、運用に問題があり十分に活用できていないケースもあると感じます。



私が無知なだけですが、子の看護休暇が年5日あるのも最近知りました…
さらに、部署によっては長時間労働や超過勤務が常態化しているケースもあり、フレックス勤務やテレワーク制度の導入も限定的です。
コロナ禍で一時的に進んだテレワークも、現在は縮小傾向にあります。
このように、公務員の福利厚生は制度面では安定していますが、実際の職場での活用や柔軟性には課題もあります。
公務員の福利厚生は安定という面では優れていますが、実際の職場で十分に活用しきれていない現状や、働き方の柔軟性においては課題があると感じています。
転職を検討する際には、制度の表面的な情報だけでなく、「実際に制度を利用している人がいるのか」「どのような働き方ができるのか」といった点にも目を向けることが重要だと思います。
まとめ:公務員の福利厚生は本当に良い?
公務員の福利厚生は、安定性・公平性が確保されている点が大きな魅力です。
住宅手当や医療費の附加給付、退職金制度など、長期的に働く上では安心感のある制度が整っています。
一方で、制度の柔軟性や選択肢の幅広さという点では、民間企業(特に大企業)が優れていることもあります。
カフェテリアプランやユニークな休暇制度、手厚い住宅支援など、公務員にはない魅力的な制度を用意している企業も少なくありません。
公務員の福利厚生の特徴
- 全国共通・法令に基づいた制度で、安定性と公平性が高い
- 宿舎制度や住宅手当で住居費を軽減可能
- 共済組合による医療補助・年金の上乗せがある
- 出産・育児・介護などライフイベントへの対応も整備
民間企業の福利厚生の傾向
- 法定外福利厚生が企業独自で整備されており、多様で柔軟
- 住宅補助、通勤手当、食事補助、特別休暇などの幅が広い
- カフェテリアプランや社内託児所などユニークな制度も登場
- 大企業ほど手厚く、福利厚生が「採用力」にも直結
公務員の福利厚生が決して劣っているというわけではありません。
ただし、「公務員だから福利厚生は良い」といった思い込みは捨てた方がよいでしょう。
転職を考える際には、自分が興味のある民間企業の福利厚生と、今の職場を丁寧に比較することが重要です。
「自分にとって心地よく働ける環境かどうか」を軸に判断することで、納得のいくキャリア選択ができるはずです。
最後までお読みいただきありがとうございました!